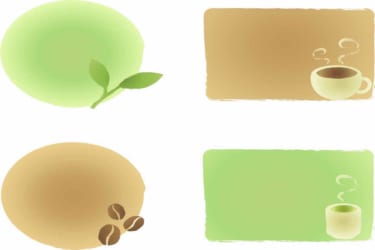あなたは自分の姿勢を気にしたことがありますか?
なんとなく猫背だと思う、首が前に出ている気がするなど、少なからず自分の姿勢が崩れていることに気づいている人も多いのではないでしょうか。
良くはないけど痛みがないから、とりあえず大丈夫だと思っているとしたら後悔するかもしれません。
なぜなら、バランスの崩れた姿勢は肥満の原因にもなるからです。
さらにやる気さえも下げてしまうとしたらどうでしょう?
今回は、あなたの痩せない理由が猫背にある可能性についてお伝えしたいと思います。後半ではセルフケアも含めて紹介していますので、是非最後まで読んで頂けたらと思います。
なぜ姿勢が崩れるのか?
まずは、姿勢が崩れる原因についてお話したいと思います。
それは、体の構造と生活環境が合っていないからです。
そもそも体は、動くことを目的とした構造になっています。
なぜなら人間含む全ての動物は、植物と違い自身でエネルギーを作ることができません。エネルギーを補給するために移動することが必要でした。エネルギー補給のためには、留まることより、移動することが生きるために必要だったと言えます。
しかし私達の生活環境はここ数百年の間に大きく変化し、食事を求めて動き回ることが必要のない生活環境へと変化しました。体の構造は、何千万年の時間をかけて進化したものであり、生活環境の変化にまだ対応できていないのです。
よって、想定されていない座位や立位での状態が続くと特定の筋肉や部位に負担が集中するため、結果的に姿勢が崩れてしまうのです。
崩れた姿勢と肥満の関係
次になぜ姿勢が崩れると太りやすくなるのでしょうか。
それには、代謝を下げてしまう直接的要因と代謝に必要な運動を抑制してしまう間接的要因が考えられます。
直接的要因1:血行不良
不良姿勢は特定の部位に大きな負担がかかります。その状態が長時間続くと、筋肉や筋膜の組織は硬く縮み、正常な伸縮ができなくなります。
そもそも体は筋肉の伸び縮みによって力を発揮するため、動きにくさや痛みを感じます。そして、縮こまった筋肉の中の血管も圧迫され流れにくくなるのです。血中には代謝に必要な酸素やホルモンが流れているため、代謝そのものが阻害されてしまうのです。
直接的要因2:内臓機能の低下
不良姿勢は内臓にも大きな負担を与えます。内臓は、頭蓋腔、胸腔、腹腔と呼ばれる三つの空間に収まっています。不良姿勢は、特に胸腔と腹腔を圧迫しやすいため、その中に収まっている内臓に慢性的ストレスを与え続けます。姿勢が悪くて呼吸が浅い、消化不良を起こしやすと言われるのはこのためです。
基礎代謝のほとんどは内臓によって代謝されているため、内臓機能の低下は基礎代謝の低下に大きく影響します。
間接的要因1:怪我リスクが増大
姿勢が悪い人は背骨のわん曲がなかったり、バランスが崩れてしまいます。背骨は体にかかる負荷を受け流すために重要を担っています。背骨が機能しない状態で運動すると、首や腰を痛めるリスクも高く、運動強度も上がりません。
間接的要因2:モチベーションの低下
運動を続ける上で重要なモチベーションと姿勢が密接な関係がある事を知っていますか?
いくつか原因はあるのですが、その一つに脳疲労の問題があります。日々のストレスや疲れを取るために、脳も休んだり老廃物を処理する必要があります。そのために重要なのが、脳脊髄液です。脳脊髄液は、身体でいうリンパ液に近い働きをしており水分量の調節や老廃物の処理をします。リンパ液が詰まると浮腫むように、脳脊髄液の流れが悪いと脳も浮腫みストレス状態が続きます。そのため、脳の機能低下が低下しモチベーションの低下を起こすとされています。
これらの要因は複雑に絡みあっているため、どの要因がどれくらい影響してか考えるを考える必要はありません。ただ、普段の何気ない姿勢にこれだけ肥満の可能性があるということは理解しておきましょう。
姿勢を崩れにくくする座り方・立ち方
はじめにお伝えしたように、人間はもともと動くことを目的とした構造になっているため長時間同じ姿勢をとってことは向いていません。しかし仕事や生活の問題で、どうしても座り姿勢や立ち姿勢が多いという方に、負担を少なくして不良姿勢をなりにくいポイントをお伝えします。
座り方のポイント
- お尻ではなく太ももの裏で座る
これは意外に思われるかも知れません。良く骨盤を意識して座る方がいますが、現代人は骨盤が後傾してい場合が多く、骨盤を立てることばかり意識して力が入った座り方になってしまいます。それより自分の重さがどこに掛かっているかを意識すると、自然なS字を保った座り方ができます。
- 目線を上げる
私たちが首や腰が曲がりやすいのは、目線が下がるためです。これを防ぐためには、机でものをかくとき、パソコンのモニターの位置を意識して下さい。スマホや本を読むのが多い方は、目線の高さで読むを意識しましょう。
立ち方のポイント
- つま先やかかと重心にならない
立っているときは、体の重心が足裏全体にかかっていることが重要です。つま先や踵にかかってしまうと、余分な力を入れて立つようになり筋肉や骨のバランスを崩してしまいます。もし全体だと分かりにくい場合は、内くるぶしと外くるぶしの中間をイメージすると分かりやすくなります。
- 身体が吊られているイメージを持つ
これは特に日本人が苦手な腸腰筋を機能させる方法です。腸腰筋は腰痛と関わりが深い筋肉でもあり、立ち姿勢を保つ際に働く抗重力筋の一つです。上半身と下半身を繋ぐ唯一の筋肉でもあるため、バランス良く立つためにはとても重要な筋肉です。腸腰筋を上手く使うことで、股関節で体重を支えることができるため無駄な筋力を使わずに楽に立つことができます。
まとめ
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
姿勢が崩れた状態は良くないと知っていながらも、なかなか改善できなかった人もいるでしょう。けれど、これだけのリスクがあるとわかれば、少しくらい生活の中で意識したいと思われたはずです。
そのちょっとした意識が改善の鍵になります。
この記事がお困りのあなたのお役に立てたのなら幸いです。